野球には「柔軟性が必要」と言われます。
その手段としてストレッチがありますが、筋トレなどと比べるとモチベーションが湧きにくいもの。
柔軟性がどのように野球のパフォーマンスに関わっているのか?
その理由について理解するとモチベーションが高まり、柔軟性アップからケガ予防、パフォーマンスアップできるかもしれません。
今回は、
と、レジェンド級にトレーナーとしてご活躍中の中垣征一郎氏の唯一の著書「野球における体力トレーニングの基礎理論」から、柔軟性のトレーニングについて言及されている部分をご紹介します。
柔軟性とは

人間は身体を曲げたり(屈曲)、伸ばしたり(伸展)、回したり(回旋)、ねじったり(捻転)することができ、またそれらを組み合わせて様々な運動ができるが、それらはすべてその運動に関与する身体各部位の関節の種類(特性)によって決まる。
・肩:球関節
・肘:蝶番関節など
・手首:らせん関節など
・手指:蝶番関節など
・股:臼関節
・膝:らせん関節など
・足首:らせん関節など
・脊柱:平面関節など
柔軟性は、様々な運動の基となる「関節の可動性」を表す体力の要素である。
柔軟性に優れると、
①関節の可動範囲が大きくなるので、大きなパワーを発揮することができる
②ケガの防止に役立つ
などの効果が得られる。
このために、柔軟性は投打走跳などの多彩な動きが含まれる野球においては大切な体力要素である。
なお実践の場で「動きが柔らかい、かたい」という会話をよく耳にする。
これは関節の可動性を表す柔軟性よりも、より合理的・効率的に動くことができる能力である調整力や技術との関わりが深いので、ここでの柔軟性とは異なるものであろう。
柔軟性の評価法
柔軟性の優劣は、関節の最大可動性で評価されている。
一般的な測定項目には、長座体前屈がある。
野球においては肩関節(前後、回旋)、股関節(前後・左右開脚、回旋など)、脊柱(体捻転)の柔軟性が重要であるが、これらを精度よく測定するのは難しい状況にある。
柔軟性に影響する要因

関節の最大可動性に影響する要因には、
①関節部位の形状
②靭帯の弾力性
③筋や腱の伸展性
④神経機能
があげられる。
特に④神経機能は急激な筋や腱の伸展に対するケガの予防などのために大切である。
具体的に言えば、例えば身体を前屈すると、ハムストリングが伸ばされて痛みを感じ、それ以上は前屈できないことがある。
これは、急激に伸ばされたことをハムストリングが感知し、瞬時に危険を回避するためにハムストリングに大きな力を発揮させ、前屈をさせないようにしているからである。
ここには、筋→脊髄→筋への神経回路(脊髄反射または伸張反射)が関与している。
したがって、柔軟性に優れるためにはこの伸張反射を抑制できることが大切になる。
PNF(固有受容器神経筋促通法)はこれに着目した施術技法、トレーニング法でもある。
柔軟性のトレーニング法とその留意事項
柔軟性のトレーニングにおいては、静的ストレッチングと動的ストレッチングがよく行われている。
すでに、身体各部位の屈曲、伸展、回旋、捻転などに関わる様々な運動が開発されており、その行い方も概ね確立されている。
ここでは、実践現場で行われているストレッチングや柔軟性トレーニングの主な留意事項を述べることとする。
①ペアで行うストレッチ運動を取り入れる
②動的ストレッチ運動を取り入れる
③野球の動きと関連のある専門的なストレッチ運動を取り入れる
④状況に応じてPNFなどの徒手抵抗運動を取り入れる
⑤ウォームアップやクールダウンのみでなく、主トレーニング(主練習)の中でもストレッチ運動を随時取り入れる
⑥発達期の早期からストレッチングを取り入れる
ペアで行うストレッチ運動を取り入れる
例えば、うつ伏せでの体後屈をペアで行う(補助者が実施者の脇の下から手を入れて、実践者を持ち上げる)。
これにより、柔軟性の限定要因の一つである筋力の影響を軽減できるので、胴体を大きくそらすことができる。
動的ストレッチ運動を取り入れる

これにより、一方向だけの静的ストレッチ運動の不備を少なくできる。
肩関節(球関節)や股関節(臼関節)のような多方向に動く関節では、インナーマッスル(深層筋)も伸展できるので、特に重要である。
野球の動きと関連のある専門的なストレッチ運動を取り入れる
これにより、野球のパフォーマンスの向上のみでなく、野球によるケガの防止にも役立つ。
状況に応じてPNFなどの徒手抵抗運動を取り入れる
PNFなどを行うことにより、一時的に柔軟性や筋力を高めることができる。
例えば、投手が数イニング投げて疲れが出てきたときに行うと、柔軟性や筋力の回復が期待できる。
また、傷害からの復帰や、準備機、試合期の柔軟性や神経機能の調節や改善においても効果が期待できる。
ウォームアップやクールダウンのみでなく、主トレーニング(主練習)の中でもストレッチ運動を随時取り入れる
これにより、野球の動きと関連のある専門的な柔軟性を高めることができる。
また、本練習による疲労の回復やケガの予防に役立つ。
ストレッチング運動は身体にそれほど大きな負担をかけることはないので、体調管理のためにも絶えず取り入れるようにする。
発育期の早期からストレッチングを取り入れる
柔軟性は、調整力と同じように、発育発達期から大きなトレーニング効果が得られるので、早めに取り入れるようにする。
柔軟性とパフォーマンス
柔軟性に優れ、関節の可動範囲が広いと大きいパワーを発揮するために有利である。
肩関節の柔軟性とスローイング

野球においては、肩の外旋可動域の優劣が投球・送球のスローイング能力に影響する。
肩の外旋可動域が極端に低い野球選手に、肩が強いと言われる選手はいないと言ってもよい。
スローイング時に腕のスイング角速度を得るためには、肩関節の外旋の可動域がある程度確保されることが非常に大切である。
また、腕をスイングするための柔軟性には、
・肩甲上腕関節の可動域
・胸郭(胸鎖関節、胸肋関節、肋椎関節などを含む)の可動域
・肩甲骨と胸郭(肩甲胸郭関節)の可動域
など様々な柔軟性が関与する。
股関節の柔軟性と守備・投球
捕手や内野手に要求される下肢の深い屈曲姿勢における捕球から送球への動作は、股関節周辺の一定水準以上の柔軟性を確保して初めて可能なものである。
また、投手が投球時にストライドを確保しながら回転動作を行うためにも股関節周辺の柔軟性が重要である。
このように、下肢の深い屈曲姿勢での高強度の運動や、肩や股関節周辺の大きな回旋運動を強いられるスローイングなど、野球独特の運動技術における傷害予防の観点からも柔軟性は重要な役割を果たす。
おわりに
最後にまとめます。
・人間は身体を曲げたり(屈曲)、伸ばしたり(伸展)、回したり(回旋)、ねじったり(捻転)することができ、それらを組み合わせて様々な運動ができる
→柔軟性は、様々な運動の基となる「関節の可動性」を表す体力の要素
・柔軟性に優れると、
①大きなパワーを発揮することができる
②ケガの防止に役立つ
などの効果が得られる
・投打走跳などの多彩な動きが含まれる野球において大切な体力要素
・実践の場での「動きが柔らかい、かたい」
→「柔軟性」よりも、より合理的・効率的に動くことができる能力である「調整力」や「技術」との関わりが深い
・関節の最大可動性で評価
・一般的な測定項目には、長座体前屈がある
・野球においては肩関節(前後、回旋)、股関節(前後・左右開脚、回旋など)、脊柱(体捻転)の柔軟性が重要
→これらを精度よく測定するのは難しい
・関節の最大可動性に影響する要因は以下。
①関節部位の形状
②靭帯の弾力性
③筋や腱の伸展性
④神経機能
・特に④は急激な筋や腱の伸展に対するケガの予防などのために大切
・例)身体を前屈→ハムストリングが伸ばされ痛みを感じる→それ以上の前屈不可
→急激な伸長をハムストリングが感知し、瞬時に危険を回避するためにハムストリングに大きな力を発揮させ、前屈をさせないようにしている
・筋→脊髄→筋への神経回路(脊髄反射または伸張反射)が関与
→柔軟性に優れるためにはこの伸張反射を抑制できることが大切
①ペアで行うストレッチを取り入れる
②動的ストレッチを取り入れる
③野球の動きと関連のある専門的なストレッチを取り入れる
④状況に応じてPNFなどの徒手抵抗運動を取り入れる
⑤ウォームアップやクールダウンのみでなく、主練習中でもストレッチを随時取り入れる
⑥発達期の早期からストレッチングを取り入れる
・肩の外旋可動域
→スローイング時に腕のスイング角速度へ
→肩の外旋可動域が極端に低い野球選手に、肩が強いと言われる選手はいない
→肩関節の外旋の可動域がある程度確保されることが非常に大切
・腕をスイングするための柔軟性には、
・肩甲上腕関節の可動域
・胸郭(胸鎖関節、胸肋関節、肋椎関節などを含む)の可動域
・肩甲骨と胸郭(肩甲胸郭関節)の可動域
など様々な柔軟性が関与
・捕手や内野手などの捕球から送球への動作
→下肢の深い屈曲姿勢が要求される
→股関節周辺の一定水準以上の柔軟性を確保が必要
・投手が投球時にストライドを確保しながらの回転動作
→股関節周辺の柔軟性が重要
いかがでしたか?
子どもの頃から、柔軟性とパフォーマンスとの関係を理解してトレーニングできると、ケガ予防しながら着実にパフォーマンスアップできそうですね。

手っ取り早く柔軟性を高めたい方は、下の記事は本当におすすめ!
より深く柔軟性のトレーニングについて知りたい方はこちらをどうぞ。
では。


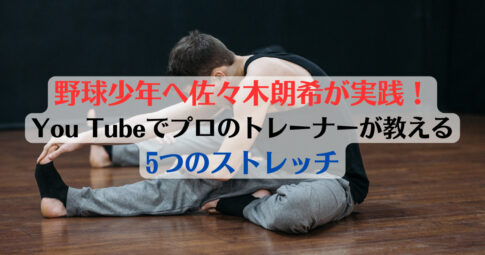
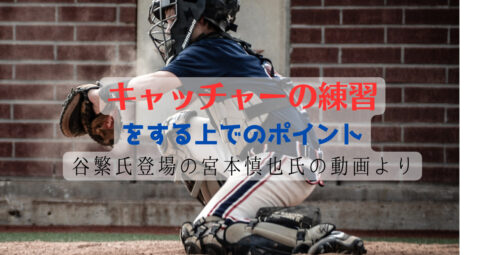
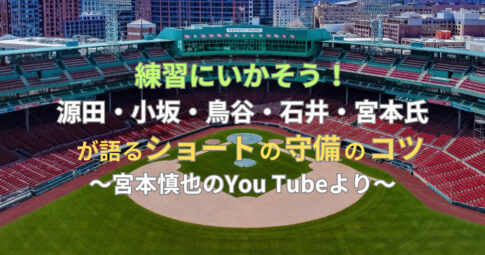
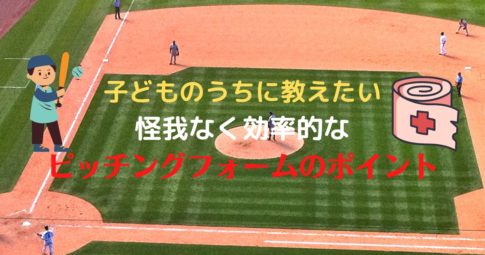

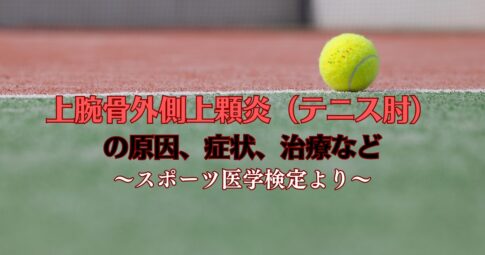
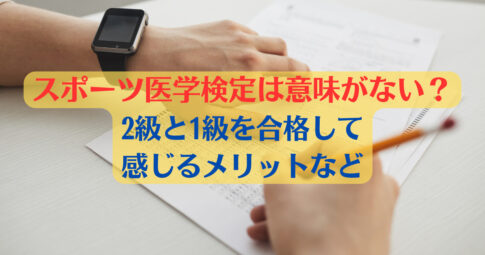
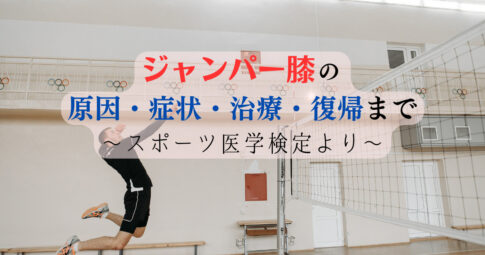
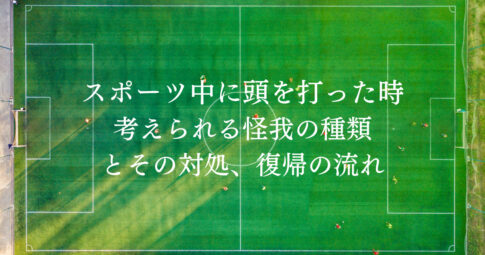
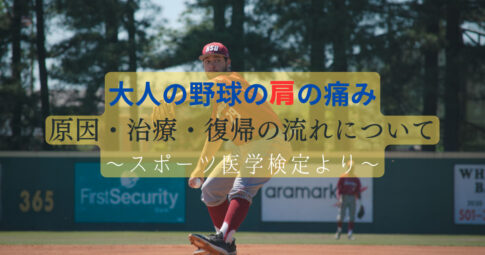
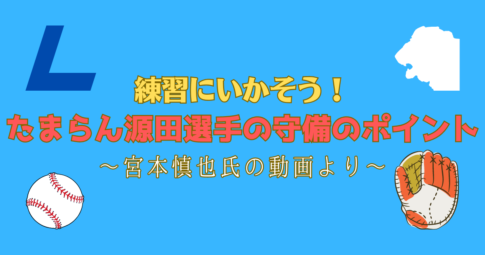

・プロ野球日本ハムのトレーナー(2004年〜2010年、2013年〜2017年)
・ダルビッシュ有選手の専属トレーナー(2012年)
・MLBのパドレスのトレーナー(2017年〜2018年)
・現オリックス・バファローズ巡回ヘッドコーチ(2019年〜)