野球は攻撃と守備があり、バッティングがすべてではありません。
しかし…本当はヒットやホームランを打って活躍したい。
子どもから大人まで、全ての野球人の素直な思いではないでしょうか?
今回はそんな思いに応えるべく、
という有名なトレーナーの著書から、
・運動力学からみたバッティング
・統計学や運動学、解剖学などからみたフライボールスイング
についてご紹介します。
キネマティクス(運動力学)からみたバッティング
まずは、
・プロ野球日本ハムのトレーナー(2004年〜2010年、2013年〜2017年)
・ダルビッシュ有選手の専属トレーナー(2012年)
・MLBのパドレスのトレーナー(2017年〜2018年)
・現オリックス・バファローズ巡回ヘッドコーチ(2019年〜)
と、レジェンド級にトレーナーとしてご活躍中の中垣征一郎氏の唯一の著書「野球における体力トレーニングの基礎理論」から、バッティングについて言及されている部分をご紹介します。
端的に言うと、一連の動作をコマ送りに分けて分析していくのが「運動学」。
一方、一連の動作を目にはみえない「力の方向」を含めて分析していくのが「運動力学」です。
バッティングは、連続写真をもとに「体の開きが…」「上半身と下半身の捻転差が…」「股関節の内旋が…」といった「運動学」の観点で語られるものが多いと思います。
その中で、「運動力学」の観点でプロ中のプロのトレーナーがバッティングを分析している貴重な内容です。
「野球における体力トレーニングの基礎理論」の「打撃理論まとめ」より
打撃動作を考える際に、打者(打撃)のタイプに関わらず押さえるべき課題として以下のようなことが考えられる(右打者の場合)。
①体重移動は右脚が地面を押すことによって投手方向にコントロールされているか
②投手方向に対して水平方向に近い直線的な体重移動を行っているか
③適切な左脚の踏み込みによって地面反力を獲得できているか
④打撃動作全体の回転軸から近い距離、すなわち身体と近い距離でバックスウィングが加速しているか
⑤地面反力による「カベ」により、上体からバットスイング動作へと続く回転動作の支点として左股関節をしっかりと固定できているか
⑥バットスイングが地面反力による「カベ」を突破するように、骨盤および胴体の回転動作とスウィング動作が行われているか
これらの項目は、ひとつひとつ独立したものではなく、それぞれが必ず続いて起こる動作に対して意味を持つ。
①と②が適切に行われてこそ③が達成されやすくなり、④〜⑥も①〜③が適切に行われてこそ、一連の技術として達成しやすくなる。
それぞれの要素が他の要素と絡み合いながら打撃動作としてのまとまりを持つのである。
下肢で行われる体重移動から上肢の動きまで、それぞれが続いたり重なったりしながら首尾よく機能したときに、一つのまとまりを持つ動作になる。
打撃動作においても、体重移動からバットスイングまでのそれぞれの動作は、次の局面への予備的な動作であり、時間的・空間的な予測のもとで続いて起こる動作を先取りしながら遂行される。
これによって効果的な動作が可能となると同時に、中心から抹消へと連続するSSCの連鎖による爆発的な力の発揮が行われるのである。
打撃動作を一連の運動としてとらえて説明することを試みてきたが、打撃は投球に対応して変化する。
打撃動作において爆発的に力を発揮するための動きを身につけると同時に、多種多様な投球に対して、フルスイングではなくとも力を爆発的に発揮できる能力もまた重要であろう。
多様な状況に応じて力を爆発的に発揮し、バットとボールの的確なコンタクトの確率を上げるために、体重移動に続いて左脚を踏み込みながら、バットスイングを効果的に加速させる動きを考えることが大切でなかろうか。
また、打撃動作における力の発揮がどのように行われるかを考え、トレーニングの目的や方法を考えることが大切ではなかろうか。
ここまで打撃動作について考えてきたが、いずれもこれが動きのスタンダードであるということを明確にしようとしてきた訳ではない。
トレーニングを進めていく上で参考になると考えられる動きのポイントと、個人の身体的または技術的特徴を特に考慮せずに、運動の原則を背景にして説明することを試みてきた。
運動技術には原則を背景に習得されるべき側面と、個人の特徴によって原則のどの部分を強調するか、または原則からどれくらい外れながらも動きの全体的な調和をとるか、これらの試行錯誤によって習得されるべき側面があると考えている。

著書の中ではもっと詳細にポイントについて述べられています!
フライボール革命からみたバッティング

次に近年、バッティングの主流になりつつあるフライボールについて。
野球をしている人なら一度は耳にしたり目にしたりあると思われる、間違いないレジェンドトレーナー立花龍司氏の著書「科学に基づくフライボール打法」から、
・最新科学からフライボール打法が好成績につながる根拠
・解剖学や運動学からフライボール打法を生み出すメカニズム
について言及されている部分をご紹介します。
「科学に基づくフライボール打法」より「ゴロとフライの打球結果のデータ比較」
これまで「フライよりゴロの方がヒットになる確率が高い」とイメージを抱く人は多かったと思います。
また、日本では子どもの頃から「上から叩け!」「ゴロを打て!フライは打つな!」「簡単にフライを打つな!」などと言われ続けた人が多いはずです。
昭和に生まれ、平成の時代に野球をしてきたアラフォー世代の私もまさにそういう指導をされて来ました。
しかし、近年の高性能解析システムによるデータ分析で以下のことが分かりました。
「2016年MLB全打者のフライとゴロの成績比較」
フライ=打率.241、長打率.715
ゴロ=打率.238、長打率.258
さらに2017年、もっと詳しくデータを見てみると、次のような結果が出てきました。
打球の種類 起こった割合 安打になる確率 長打になる確率 本塁打になる確率 ゴロ 45% 25% 2% 0% ライナー 25% 63% 23% 3% 内野フライ 7% 2% 0% 0% 外野フライ 22% 27% 23% 18% 2017年MLB全打者の打球の種類別結果
つまり、この結果はゴロよりもフライの方か、長打だけでなく単打の確率も高いことを示しています。
始めからゴロではなく、フライを狙う方がよい結果を生む可能性があるということです。
バレルゾーンとは
さらに外野フライに着目し、強打者のバッティングについて、バットとボール「打球速度(初速)」と「打球角度(発射角)」を組み合わせて分析しました。
すると、好成績を上げているスイートスポット(最適打球点)をみつけました。
それが「バレルゾーン」です。
フライの中でも、外野フライを分析した結果、近年話題になっている「バレルゾーン」なるものが見つかりました。
バレルゾーンの打球速度と打球角度
具体的には、バレルゾーンの最低条件は、打球速度が158キロ以上であること。
打球速度が158キロだった場合、打球角度26〜30度(角度4度の幅)で打てば、バレルゾーンに入った打球とみなされます。
世界最高峰のメジャーリーグの打撃を分析した結果、バレルゾーンの最低条件は「打球速度158キロ」。
その打球速度158キロかつ打球角度26〜30度であれば、バレルゾーンに入った打球とのことです。
2016年のメジャーリーグではバレルゾーンに入った全打球を調べた結果、打率.822、長打率2.386と全ての打席を平均して2塁打以上という驚愕の数字が導き出されています。
なお、打球角度の条件は、打球速度が上がれば上がるほどは広がります。
100マイル(約161キロ)を超えた打球の場合、打球速度が1マイル(約1.609キロ)上がれば打球角度の幅も2〜3度ずつ上がります。
打球速度 打球角度 角度の幅 158キロ(最低条件) 26〜30度 4度 161キロ 24〜33度 9度 187キロ 8〜50度 42度 バレルゾーンの例
打球速度が上がれば、打球角度の幅も広がります。
つまり、打球の角度によっては外野フライになっていたものが、打球速度が高くなると外野手の頭を超え、長打になったり、スタンドインする可能性が高まるという訳です。
ただ打球速度が速ければいい訳ではありません。
例えば、打球速度が161キロだったとき、バレルゾーン「内」の打球角度27度であればホームラン率52%ですが、バレルゾーン「外」の20度であればホームラン率は3%まで低下します。
したがって、バレルゾーンの打球角度の範囲で打つことが好成績に結び付く訳です。
打球速度を速くするだけでなく、バレルゾーン内の打球角度で、バットとボールのコンタクトさせる精度を上げることが、長距離砲になるためには必要となります。
バレルゾーンに必要なインパクトとスイングスピード
では、158キロの打球速度を生み出すためには、どれだけのスイングスピードが必要なのでしょう?
打球速度が最高に達するのはどういうケースかと言うと、向かってくるボールの軌道に合ったスイング軌道で、ボールの芯とバットの芯が強く衝突したときになります。
バレルゾーンも158キロ以上の打球速度が必要になるため、バットの芯で打つことが前提と考えられています。
なお研究によれば、158キロ以上の打球速度を出すためには最低でも128キロ以上のスイングスピードが必要になるとのことです。
答えは「128キロ以上」のスイングスピードが必要とのことです。
そのスイングから生み出された力を、158キロものスピードを持つ打球に変換する。
その前提条件としては、当然タイミングよくバットの芯でボールをとらえる必要はあります。
その一方、打球の飛距離が最高に達するケースというのは、発射角が26〜30度になったときと、まさにバレルゾーンの条件と一致しています。
その打球角度26〜30度にするためには、ボールのど真ん中(芯)から6ミリ下を約19度上向きの軌道で衝突させる必要があります。
今度は打球の飛距離に視点を移すと、最高飛距離に達するケースはバレルゾーンと同様の角度26〜30度だったということです。
具体的には、ボールのど真ん中(芯)から6mm下を、約19度上向きのバットの軌道でとらえる必要があるとのことです。
やはり、スピードだけでなく、正確なコンタクトの技術が求められるようですね。
バレルスイングのまとめ
つまり話をまとめると、バレルゾーンで打つためには、
①地面から約19度上向きのスイング
②スイングスピード128キロ以上
③ボールの芯から6ミリ下をバットの芯で強く叩く
④158キロ以上の打球速度を出す
ことが求められる、ということになります。
どれくらいのアッパースイングが必要か

ここからは、前述されている上向きのスイングの必要性の根拠と、その角度の程度についてです。
最もヒットが出やすいのは、向かってくるボールの軌道と同じ軌道でスイングすること。
前述の通り、同じ軌道で打つことができれば、打球速度が最高に達する可能性も高くなるのです。
そして地球上では重力が発生するため、わずかな入射角に合わせた緩やかなアッパースイング軌道が求められる。
ならば具体的にはどれくらい「緩やか」であれば良いのでしょうか。
地球上で野球をする以上、重力の影響を受けます。
そのため、ピッチャーの放つボールはどんなに速くても、伸びるように感じるボールであっても、投球の軌道を線で表すと上から下へ向かう線になります。
その中で、ダウンスイングもしくはレベルスイングだと、そのバットの軌道を線で引くと、投球の軌道と交わるポイントは一点のみになります。
かたや、投球の軌道の線の傾きとバットの軌道の線の傾きを近く作れば、両者が重なる線ができます。
つまり、ボールとバットがコンタクトできるポイントの幅が広がります。
これが、アッパースイングがよりヒットを生み出す確率を高める根拠となります。
投手が投げるストレートはどれくらい落ちているのか

次に、ピッチャーの放つボールの軌道の線はどれくらい下向きの角度があるのでしょう?
メジャーリーグの投手たちのストレート系は平均93マイル(約150キロ)で、打者に向かってくる際は約5度の入射角があると言われています。
一方、日本のプロ野球におけるストレート系の平均球速は143.2キロ。
ある研究報告によると入射角は8度前後と言われており、「前後」という言葉の意味を広くとらえると「6度から10度くらいまで」と考えるのが妥当でしょう。
つまり、ある程度のスピードがあってなおかつ「伸びるボール」も投げてくる一流のレベルに合わせて言うのであれば、ボールの軌道には「5度から10度まで」の角度がある。
プロ野球からメジャーリーグといった一流のレベルでは、ボールの軌道には「5度から10度まで」の角度があるようです。
したがって、ヒットを量産して打率を求めていきたい場合は、スイング軌道が合う約5〜10度上向きのスイング軌道が理想と言えるでしょう。
そうすれば結果的に最高の打球速度でライナーになり、63%の安打率と23%の長打率を得ることができます。
そのため、ホームランや長打を打つパワーヒッターというより、ヒットを量産するアベレージヒッターを目指したい選手は、その5〜10度に合わせたアッパースイング軌道が理想となります。
なお、高校生以下のステージでは平均球速がグッと遅くなるため、ボールの入射角がさらに大きくなることが予想されます。
ということは、さらに上向きのスイングの方がボールの軌道に合う可能性が高い。
こちらについては、今後の研究結果を待ちたいと思います。
あくまで、前述のピッチャーが放つ下向きのボールの軌道の線の角度5〜10度はプロ野球からメジャーといった一流レベルの話です。
そのため、よりピッチャーの球速が劣る高校生以下のカテゴリーになると、よりアッパースイングの軌道が、ピッチャーから放たれるボールの軌道と一致することになります。
理屈ではそういうことになりますが、データの集積による研究結果はまだ出ていないとのことです。
アッパーの角度はホームランバッターとアベレージヒッターどちらを目指すかで変わる

ただ、いずれにしてもアッパーのスイング軌道が理想であることに変わりはありません。
そして、将来的にホームランバッターを目指すなら「約19度上向きのスイング」。
アベレージヒッターを目指すなら「約5〜10度上向きのスイング」。
もちろん厳密には、投手は様々な方向に動く変化球も投げてきますし、同じストレートでも高低やコース、緩急の差などがあり、1球ごとに入射角は細かく変わってしまうので、これが絶対だと言えるものではありません。
それでも確率よく結果を残そうと思えば、やはりこの2種類のスイング軌道が一つの目安になるのではないでしょうか。
バレルゾーンの項で前述しているように、ホームランバッターのような長距離砲を目指すのであれば「約19度上向き」のアッパースイングが必要になります。
そのアッパースイングを習得しつつ、128キロ以上のスイングスピードを生み出すフィジカルの強化、それを打球速度158キロ以上に変換させるボールコンタクト技術。
それら全てが必要になります。
そして、ピッチャーはストレートだけでなく、変化球で緩急をつけたり、高低・外内を変えるなどバッターを翻弄してきます。
それによってピッチャーの放るボールの角度も変わります。
バッターはあくまで目安としてアッパースイングの角度を身につけ、投球に合わせて臨機応変にスイング角度など変化させる必要がありそうですね。
飛距離と打球の回転方向、回転数の関係
ここからは、打球の質についてです。
単純にボールを遠くに飛ばしたい場合、打球の回転方向と回転数の2つが重要になります。
まず回転方向は「揚力」を踏まえ、上向き回転(逆回転、バックスピン)が掛かること。
ボールを遠くに飛ばすためには、打球に上向きの回転、逆回転であるバックスピンをかける必要があるようです。
そうすることで、揚力、つまり浮き上がる作用が働きます。
揚力とは物体が流れていく方向に対して垂直な成分。揚力の方向は回転軸の向きによって決まる。揚力の大きさは回転スピードと回転軸の向きに関係。回転軸の向きがボールの進行方向と平行に近づくほど小さくなり、直交に近づくほど大きくなる。
そして回転数は、毎分4000回転が理想的です。
回転数が高ければ高いほど良いという訳ではなく、毎分6000回転まで上がると非常に高く上がりすぎた凡フライになってしまい、飛距離が出ません。
そう考えると、約19度上向きのスイングでボールの芯から6ミリ下を叩くバレルスイングというのは、毎分4000回転のバックスピンを与えやすいスイングと言えるのでしょう。
バックスピンかつ毎分4000回転の回転数が最も飛距離が出る。
回転数が毎分6000回転になると、上空にあがり過ぎ、飛距離が出ない。
そういう研究結果があるようです。
アッパースイングと打球の回転
次に、バットとボールのコンタクトする位置による回転の変化についてです。
また、ボールの軌道に合わせた約5〜10度上向きのスイングにしても、やはりメリットがあります。
ボールの軌道とバットの軌道を合わせた場合、ボールの中心よりも上を叩くと打球は下向き回転(順回転)で飛んでいきます。
また、ボールのど真ん中を叩くと打球はほぼ無回転で飛んでいきます。
ただし、インパクト後にはバット自体が下向きにローリングしていくので、ややバックスピンが掛かることもあります。
そしてボールの中心よりも下を叩くと、打球は上向き回転で飛んでいきます。
実はこの3つのパターン、どれになっても良い結果になりやすいのです。
「アッパースイング」でどうボールのどの位置をとらえたかによって、ボールの回転は以下のようになります。
・ボールの中心より上→下向き回転(順回転)
・ボールの中心→無回転
・ボールの中心より下→上向き回転(バックスピン)
スイングとインパクトの場所で変わる打球の回転
今度はアッパーかダウンか、バットスイングの軌道別で、打球の回転を考えていきます。
バットでボールの中心よりも上を叩いた場合
例えばバットでボールの中心よりも上を叩くと基本的に打球はゴロになりますが、もしダウンスイングだったとしたら逆回転となり、地面に接触するとスピードが一気に減少してしまいます。
しかし、アッパースイング軌道であれば順回転。
バウンドしてもなかなか減速せず、打ち損ないの当たりが内野手の間を鋭く抜けていく可能性も出てくるのです。
ボールの中心より上をバットで叩いた場合、基本はゴロになります。
その際のバットの軌道がダウンスイングであれば、地面と接触するとスピードが減速する逆回転になってしまいます。
一方、アッパースイングであれば、バウンドしても減速しにくく、内野の間を抜けやすい順回転になるのです。
バットでボールのど真ん中を叩いた場合
では、ボールのど真ん中を叩いたらどうでしょう。
ダウンスイングであればそもそも上から叩いている訳ですから、そのケースでも逆回転のゴロになります。
しかしボールの軌道に合わせた上向きのスイングであれば、無回転でライナーが飛んでいく。
その打球はサッカーの無回転シュートと同様、空気抵抗の影響で不意に変化することがあるため、守っている野手からすると非常に捕りにくいものです。
また、バットのローリングの影響でやや逆回転が掛かれば、揚力も合わさって飛距離が伸びます。
次に、ボールのど真ん中を叩いた場合です。
ダウンスイングであれば、上から叩いているため、地面と接触するとスピードが減速する逆回転になってしまいます。
一方、アッパースイングであれば、無回転のライナーになります。
サッカーの無回転シュートのように変化することがあり、内野手にとって厄介な打球になり出塁の確率が上がります。
そして逆回転になることもあるようで、そのときは揚力が生まれ、飛距離が伸びるといいます。
バットでボールの中心よりも下を叩いた場合
さらに、ボールの中心よりも下を叩いた場合。
基本的に打球はフライになりますが、ボールの軌道に合わせた上向きのスイングであれば強い逆回転が掛かり、ホームランの可能性が出てきます。
ちなみに、ボールに逆回転を与えようとすると一生懸命にダウンスイングをしてボールの下を叩くと、回転数は増えるけれども打球速度が上がらず、平凡なフライになってしまいます。
ボールの中心より下をバットで叩いた場合、基本はフライです。
前述しているように、アッパースイングであれば、逆回転による揚力が生まれ、外野の頭を超える長打につながりやすくなります。
つまり、ボールの軌道に合わせた上向きのスイングをすれば、ボールの中心を狙ってそのまま行けばヒットや長打。
さらにミスショットで少し上にずれてもゴロでヒットになりやすく、少し下にずれると今度はホームランの確率が高まってくれるのです。
一定の力強いアッパースイングを身につければ、多少のバットとボールのコンタクト率の低さがあっても、ゴロが内野の間を抜けたり、フライが外野の頭を超える確率を高めることを示しています。
アッパースイングを作り出すメカニズム

ここまで、ダウンスイングよりもアッパースイングの方が、データ的にも、物理的にも好成績を生む可能性が高いこと、好成績を生むために求められるアッパースイングの質についてのお話でした。
今後は、質の高いアッパースイングを習得するための方法論についてお話を展開していきます。
まずは、打撃動作について分解していきます。
打撃動作というのは簡単に言うと「回転運動」と「並進運動」の2つで成り立っています。
体がその場でクルッと回転することが「回転運動」で、物理学的に並行にまっすぐ進むことが「並進運動」です。
簡単に打撃動作を2つに分けると、「並進」と「回転」の動作になります。
「並進」は、胸の向きはそのままで後ろ足から前足へ体重を移動させるフェーズになります。
そして「回転」は、投球に合わせて胸を回しながらバットを出していくフェーズです。
並進運動を大きく使うデメリット
そして、回転運動と並進運動をいかに組み合わせるか。
これがスイングの根幹となるのですが、選手によっても2つの運動を同じ割合で使う人もいれば、どちらかに偏って使う人もいます。
バッティング動作において「並進」と「回転」動作の割合は人それぞれ。
ただし、ボールは投手方向から自分に向かって進んでくるものです。
ということは、投手方向への並進運動が大きすぎるとボールにわざわざ近づいていることになり、体感スピードがより速くなって詰まりやすくなってします。
またボールとの距離が縮まる分、軌道も見極めにくくなります。
ところが、プロも含めた日本の野球界を見てみると、打者は反動の力を得るために並進運動を大きく使う傾向にあります。
「並進」運動は、体重移動の反動のエネルギーを利用し、ボールに力を伝えることができます。
そのため、日本の打者は並進運動の比重が高い選手が多いそうです。
しかしデメリットもあります。
打者にとってボールは向かってきます。
「並進」の割合が高いということは、自ら向かってくるボールに近づいていくことになります。
するとボールの体感スピードが上がる、軌道が見極めにくいといったデメリットが生じます。
並進運動を減らし、回転運動に比重を置くメジャーの打者
現代はムービングファストボール(打者の手元で微妙に動く速球)が全盛なので、ボールをギリギリまで引きつけたい。
したがってメジャーリーグの打者たちはできる限り並進運動の中にあるムダをなくし、回転運動に比重を置いて打っています。
実際、打席内で構えた状態からほとんど動かず、ボールが来たらその場で回転しているように打っている打者もよく見かけますよね。
もちろん、そういうスイングだと位置エネルギーの移動による力を得られないため、パワーも必要となるのですが、ともかく、速いボールに対して並進力に頼るバッティングをしていては、苦戦するのも仕方ないと言えるでしょう。
日本に対してメジャーの打者は、「並進」を減らして「回転」の比重を高くしているそうです。
前述しているように、ピッチャーの平均球速が日本のプロ野球より速いため、先ほどの「並進」のデメリットを極力なくした結果と言えます。
「回転」の比重が高いということは、「並進」の反動のエネルギーをあまり使えません。
そのため、体力としての筋力や(無酸素性)パワーが必要になります。
メジャーリーガーはそうした体力を身につけるため、日本のプロ野球選手よりサイズアップしている事実は、大谷選手などみていると一目瞭然ですね。
垂直回転と水平回転に分けられる回転運動
また、「回転」運動も2つの運動に分けることができます。
筑波大学野球部助監督の奈良隆章助教は、つい最近までアメリカの大学でコーチングの研修をされていました。
そこで、日本の野球界とはまるで違う指導法に驚いたそうです。
彼いわく「アメリカは観覧車」。
どういうことかと言うと、アメリカで出会った数人のコーチは観覧車のように垂直回転を使って打つことを推奨し、メリーゴーランドの水平回転だけで打つことは良くないと考えているのだと。
よく日本の打者は両肩を平行にした状態で骨盤と一緒に体を横に回転させようとしますが、アメリカの打者は体をできるだけ縦に回転させようとするのです。
「水平」回転と「垂直」回転に分けられます。
アメリカでは、その2つを分かりやすく表現するため、「水平」はメリーゴーランド、「垂直」は観覧車に例えて、指導するそうです。
日本は「水平」に横回転をしようとするのに対し、アメリカは「垂直」に縦回転しようとする傾向があるとのことです。
体を観覧車のように縦回転(垂直回転)させればスイングはナイキマークに
体を観覧車のように縦に回転させる。
そうすると必然的にバットをボールの下に潜り込ませることになるので、つまりはアッパースイングを推奨していることになります。
バットを持って、体を縦回転させると必然的にバットのヘッドは下がり、アッパースイング軌道になります。
近年、インスタグラムなどでよく「縦回転」と言われるのを目にする方も多いと思いますが、こうしたアメリカ流のスイング方法が始まりのようです。
また奈良氏によると、アメリカで出会ったコーチの多くはスイングのイメージについて、「ナイキのマークで打て!」と言われるそうです。
ナイキのロゴマークでもある「スウィシュ」はみなさんもご存知だと思います。
これを真横(一塁側)から右打者を見たときのバットの軌道に見立てた場合、まず左側から半円を描くようにしてスイングしてバットをボールの軌道に入れていき、そこから一直線に振り上げていくということになります。
ちなみにナイキのマークの跳ね上がり具合は角度にして20度ちょっとなので、約19度上向きのアッパー軌道をイメージするにはちょうどいいのかもしれません。
アメリカでは、こうしたスイング軌道をイメージしやすくするために、「ナイキマーク」のように打つように指導されることもあるようです。
ナイキマークの跳ね上がりの角度は20度とのこと。
バレルスイングの角度に近似しており、子どもなどへスイング軌道をイメージさせるにはピッタリかもしれません。
観覧車やナイキマークをイメージすると、スイング前半に生まれる垂直回転
もちろん、水平回転がまるっきりダメだと言っているわけではありませんし、実際にスイングの中には水平回転も必要です。
ただ、こうした「観覧車」や「ナイキのマーク」のイメージを持つと、スイングの前半に垂直回転が現れます。
これがものすごく重要なポイント。
バットを上に構えた状態からボールの軌道に合わせて同じラインに入れ、さらにレベル(ボールの軌道と水平)の状態でヘッドを再加速させていくためには、スイングの前半約1/4〜1/5で垂直回転を行い、残りの約3/4〜4/5を水平回転を行うことが理想的なのです。
近年、バッティング理論で「縦回転」が盛んに言われています。
しかし、実際はベッティングには縦回転だけではなく、横回転も必要とのこと。
バッティング動作のフェーズにおいて、前半に垂直回転、後半に水平回転の成分が多くなるようです。
スイングの前半1/4〜1/5で垂直回転を行い、残りの3/4〜4/5水平回転を行うことが理想。
その前半の垂直回転を作り出すには、「観覧車」や「ナイキのマーク」のイメージを持つと効果的とのことです。
日本式の水平回転&最短距離で上から叩くとアウトサイドインのドアスイングに
日本では「回転=水平回転」というイメージが定着しており、さらに「最短距離で上から叩け」という指導者の意識づけも強いため、垂直回転をほとんど意識していない選手が多いように思います。
したがって、インパクトまでのバットのヘッドの軌道が曲線でなく直線になりがちです。
中には「上から叩け」をそのまま実行し、トップハンド(右打者の右手、左打者の左手)に力が入りすぎて、いわゆるアウトサイドイン(外から内)の「ドアスイング」になる選手も少なくありません。
かつてバッティングは、「最短距離で上から叩く」というのが主流でした。
しかし、そうするとスイングは水平回転が主になり、ヘッドの軌道は直線的になります。
好打者に共通すると言われる「インサイドアウト」ではなく「アウトサイドイン」の軌道になり、「ドアスイング」と呼ばれるスイングになります。
不十分な加速&腕だけの操作のダウンスイングで一点のポイントをとらえるためゴロになりやすい
この「上から叩く」スイングはなぜ良くないのでしょう?
では、この状態でボールを打つとどうなるか。
ヘッドを十分に加速させることができない上、バットが下降したまま体の正面(ヘソの前)に向かっていってインパクトを迎え、さらにその後もバットは下降していきます。
つまり明らかなダウンのスイング軌道となり、打球がゴロになりやすい。
しかもバットが最下点を通るのがインパクトの後ですから、ヘッドが十分に加速する直前に打ってしまうことになります。
一つは当然、ゴロになりやすい点。
あとは物理的に、「距離」と「加速」が足りない点です。
質量のあるバットのヘッドは、高い位置から低い位置までの距離が長い方が多くのエネルギーを蓄えられます。
そして、助走距離は長く、直線より曲線の方が加速が効きます。
その意味において、加速が効いた最下点でボールとコンタクトさせることができれば、強い打球を生むことができます。
直線的で最下点を迎える前にボールとコンタクトするダウンスイングは、その意味で弱い打球になってしまいます。
かと言って、そういう選手に対して中途半端にアッパーのスイング軌道の意識を持たせると、今度はスイングの後半だけ振り上げたV字の軌道になってしまいます。
イメージとしてはチェックマーク(✔️)と言えば分かりやすいでしょうか。
これだと腕だけで操作したスイングになってしまいますし、ボールをとらえるポイントもただ一点。
ミート率が悪く、何よりアッパーのスイング軌道でボールをとらえることができません。
ダウンスイングが身についた選手に中途半端にアッパースイングの意識を持たせても、腕だけでスイングの後半だけ無理に振り上げる軌道になります。
また、前半はダウン軌道なので、結局ボールの軌道とバットの軌道が交わるポイントは一点のみで、ミート率が悪くなります。
トップからスイング前半の垂直回転でバットのヘッドをボールの軌道へ入れる
前述しているように、ヒットを量産したければライナー、ホームランを量産したければフライを打つのが確率が高い。
そのためにはボールの軌道に合わせたアッパーのスイング軌道をすること、もしくは少しアッパー気味にしてバットをボールの軌道の下に潜り込ませることが重要です。
したがって、まずはトップの状態から、バットのヘッドが捕手方向への緩やかな曲線を描いてボールの軌道に入っていくことが大事。
スイング前半の垂直回転は、これを生み出すための動作でもあります。
ヒットや長打の確率を上げるためには、ピッチャーが放る上から下へ角度のあるボールの軌道に、バットの軌道を合わせる必要があります。
つまりアッパースイング。
それは、トップの状態からバットのヘッドがキャッチャー方向へ曲線を描いてボールの移動に入れることで生まれます。
つまり、それがスイング前半の垂直回転なのです。
曲線だからこそボールの軌道に入れて、振り上げやすくなるのであって、「最短距離で出す=直線で出す」ではない。
これまで多くの指導者たちが「最短距離でバットを出せ」と言い続けてきたのは、この曲線が大きくなりすぎないように注意する意味があった。
そうとらえた方がいいでしょう。
かつてはバッティングの指導は「最短距離でヘッドを出す」というのが通説でした。
しかし、今も昔も強打者の映像を見ると、ほとんどがダウンスイングではなく、ヘッドは下がった軌道に近いものがほとんどです。
昔の強打者も「最短距離」と語っていたのは、垂直回転によるキャッチャー方向への曲線が大きくなり、振り遅れたりしないようにするための意識づけだったのかもしれないと述べられています。
腕だけでのアッパースイングでは体からバットから離れる&体幹の力が利用できない
実際のところ、腕だけで操作してナイキのマークのようなアッパーのスイング軌道にしようとする人もいるでしょうが、これでは本末転倒です。
体から遠くにバットが離れて体幹の力が利用できず、さらにヘッドが落ちて大きな力が伝わりませんし、速いボールには振り遅れやすくもなってしまいます。
好成績につながるアッパースイングは腕の操作だけでは成立しません。
体幹の力を使いながらスイングを生み出していく必要があります。
水平回転を意識してアッパースイングをするとインサイドアウトのスイングに
そもそも昔から言われてきたこととして、スイングの理想は内から外に力が伝わっていくインサイドアウトだとも言われています。
ではみなさん、バットを持たなくてもいいので、実際に体を動かしてみてください。
まずは水平回転を意識しながらミートポイントに向かって最短距離で両腕を出す。
そうすると、捕手側の腕や手首をこねるようなアウトサイドインのスイングになりやすいですよね。
逆に、垂直回転を意識してアッパーの軌道でスイングをしてみるとどうか。
今度は捕手側のヒジが体に巻きついていき、インサイドアウトのスイングになりやすい。
そう考えても、垂直回転でアッパーのスイング軌道に入れることは、理にかなっていると言わるでしょう。
体の外から内へバットが出る「アウトサイドイン」ではなく、体の内から外に出る「インサイドアウト」が好打者の条件だと言われてきました。
実際に「水平回転」と「垂直回転」を意識してそれぞれスイングするように体を動かしてみると、「垂直回転」の方がバットのヘッドは体の内から外へ向かうインサイドアウト軌道になる感覚があると思います。
そういう意味でも垂直回転でのアッパースイングは、理にかなっていると述べられています。
理想的なアッパースイング軌道のまとめ
アッパースイングを作り出すメカニズムをまとめます。
全身を連動させた理想的なアッパースイング軌道を実現するためには、まずはスイングの前半約1/4、少なくとも約1/5では体が垂直回転をすること。
そして残りの動きでボールの軌道に合わせた水平回転に切り替わり、今度はバットを一気に振り上げていくことです。
そうするとインパクト前に軸足(右打者の右足、左打者の左足)の前でバットのヘッドが最下点を迎えることになり、しっかりと加速した準備万端の状態でインパクトに向かっていき、アッパーのスイング軌道を長く保ったまま打つことができます。
また最下点が捕手寄りになることで、ボールを体の近くまで引きつけても力を伝えることができます。
垂直回転と水平回転をうまく使い分けたアッパースイングの体の使い方
腕だけの操作ではない、体幹からの垂直回転でのアッパースイングの重要性は十分理解できたと思います。
ここからいよいよ、そのスイングの作り方です。
体幹の側屈で生み出す垂直回転

まず、垂直回転を行うためには体幹の側屈が必要になります。
側屈というのは、体を真横に曲げる動作のこと。
ステップした足のつま先が地面に着いた後、カカトが接地したタイミングのところで捕手側の体幹を曲げて上体をグッと傾けることで、捕手側の肩が下がり、逆に投手側の肩が上がって、体が縦に回転するようになるわけです。
なお側屈しているとき、反対側の筋肉にはエキセントリック(伸長性収縮)の負荷が掛かって、引き伸ばされている状態になります。
まず1つ目のポイントは「体幹の側屈」になります。
上のイラストのように本来人間には、50度ほど体を横に曲げる側屈の可動域が備わっています。
バットを持って、(またはそのつもりで)キャッチャー側に側屈を行ってみましょう。
すると体と一緒にバットのヘッドも縦回転するのがわかると思います。
ちなみに、その運動を作っているのは腹斜筋群になります。
ソフトバンクホークスの柳田選手など、バレルスイングと言えるバッターが登場し出した近年、プロ野球選手が「腹斜筋の故障で離脱」というニュースを耳にするようになったのは偶然ではないのです。
スイング時の側屈のためにはスイング前の予備動作を
また、スイング時に捕手側の体幹を側屈させるためには、その直前に逆の動作、投手側の体幹を側屈させておくと効果的です。
タイミングは人それぞれですし、必ずしも投手側の体幹を側屈しなければいけないわけではありませんが、自分なりに捕手側の体幹を側屈させやすいように準備を整えておくことは大切です。
また、キャッチャー側の側屈を投球に合わせて力強く行うためのコツとして、その逆の側屈、つまりピッチャー側に側屈を事前にしておくことです。
ただし、タイミングの取り方は人それぞれですので、必ずしも必要ではないと述べられています。
しかし、そうすることで相反神経抑制によってキャッチャー側の腹斜筋が伸ばされやすくなると個人的には思います。
それによってトップの高さが出るため、位置エネルギーを蓄えられるのはメリットでしょう。
また、伸ばされた分、バネのように縮みこむ力が強まる筋肉のSSC運動を利用できるのではないかとも思います。
実際、メジャーリーガーやプロ野球などそうした事前の側屈動作を取り入れているバッターは多いように感じます。
肩甲骨の下方回旋で生み出すエルボーインとインサイドアウト

垂直回転と水平回転をうまく使い分けるためには、さらにポイントが2つあります。
捕手側の肩甲骨の下方回旋(肩甲骨の下側を背骨に近づけるようにして回す動き)と、捕手側の肩甲骨の外転(肩甲骨そのものを背骨から遠ざける動き)です。
垂直回転時に捕手側の肩甲骨が下方回旋をすると、捕手側のヒジを体の内側に入れていく動き(エルボーイン)が生まれ、バットが体に巻きつくようなインサイドアウトのスイングになります。
側屈以外に重要な動きとして、肩甲骨の「下方回旋」と「外転」運動があります。
上のイラストのように肩甲骨の下側を背骨に近づけるように回す運動が「下方回旋」になり、それが2つ目のポイントになります。
体幹の側屈とともに、キャッチャー側の肩甲骨を「下方回旋」しようとすると、キャッチャー側の肘がおヘソに向かっていきます。
それが「エルボーイン」という動作になり、結果的に垂直回転とともにバットが体に巻きつくような「インサイドアウト」のスイングになるという訳です。
肩甲骨の外転で生み出す垂直回転から水平回転への切り替え

そして垂直回転から水平回転に切り替える働きをするのが、捕手側の肩甲骨の外転。
エルボーインの直前あたりからこの動きが起こることによって、ボールの軌道に入ったバットがグッと前に大きく押し出され、一直線に振り上がって全身を連動させたアッパー軌道が生まれていくのです。
なお、スムーズに水平回転へ切り替えるためには、垂直回転の最中に投手から見てバットの角度が約45度になるのがちょうどいいとされています。
そして、垂直回転から水平回転に切り替える働きをする3つのポイントが、キャッチャー側の肩甲骨の「外転」になります。
上のイラストのように、肩甲骨が背骨から離れる方向にスライドする運動が「外転」になります。
エルボーインの直前あたりから肩甲骨の「外転」によって、ボールの軌道に入ったバットが前に押し出されます。
結果的に、腕の操作だけでない全身を使ったアッパー軌道が生まれます。
なお、垂直回転から水平回転へ切り替わるタイミングは、垂直回転の最中にピッチャーからみてバットの角度が45度になるのがちょうどいいとのことです。
アッパースイングに必要な肩甲骨の柔軟性と予備動作フライングエルボー
この2つの動作を行うためには少なからず、肩甲骨まわりの十分な柔軟性が必要になります。
そしてもう1つ、予備動作として重要なのがフライングエルボーです。
先ほどの肩甲骨の「下方回旋」や「外転」などを行うには、当然肩甲骨まわりの筋肉や肩甲骨と一体となって動く鎖骨や肋骨が構成する関節の柔軟性も必要にあります。
そして、4つ目のポイントとなるのが予備動作「フライングエルボー」を生み出す、肩甲骨の「上方回旋」になります。
予備動作フライングエルボーで生み出す、スイング開始時の距離とスピード
フライングエルボーとはユニフォームにシワが寄るように捕手側のヒジを上げてグッと張り、ワキを空けて捕手側の肩甲骨を上方回旋(肩甲骨の下側を背骨から遠ざけるようにして回す動き)させた状態のことです。
フライングエルボーとは読んで字のごとく、肘が高く挙がった状態のこと。
肘といってもキャッチャー側の肘になります。
先ほどの肩甲骨の下方回旋の反対、「上方回旋」をスイング前の予備動作として行います。
肩甲骨の下側が背骨から離れるように回す運動が「肩甲骨の上方回旋」になります。
この行為には、あらかじめ上方回旋をしておくことで大きな下方回旋を引き出すという意味があります。
ワキを大きく空けておくと下方回旋する距離が長くなるため、スイングの開始時のスピードが上がり、一気に、そしてスムーズにスイングの前半で垂直回転を起こせるのです。
フライングエルボーの度合いは人それぞれで、最初からヒジを90度以上まで上げていく人もいれば、まずは80度程度に上げておく人もいます。
ただ、いずれにしてもステップする瞬間には100度以上に上げてギューッと上方回旋を強め、反動をつけてスイングに向かっていきます。
この肩甲骨の「上方回旋」を事前に行う意味は以下になります。
肩甲骨「下方回旋」の助走距離が長くなる
↓
スイング開始時のスピードが上がる
また、スイング前にあえてスイングに必要な反対の運動を行うことになります。
それにより、体幹の側屈でもお話したように相反神経抑制やSSC運動の作用で、肩甲骨下方回旋に収縮する筋肉を伸張させ、バネのように一気に縮こまる働きを促進させる効果もあると思われます。
ちなみに、フライングエルボーの動作で肘をどの程度挙げるかは人それぞれのようです。
一方、ワキを締めている打者というのは、下方回旋の距離が短くなってしまいます。
走り幅跳びの助走をイメージしてもらえば分かりやすいですが、これは助走の距離が短く反動のない状態で飛んでいるのと同じこと。
カナヅチと言えば、後ろに振り上げることなくパッと小手先で杭を打っているのと同じです。
昔は指導者から、バッティングは「脇を締めろ」とよく言われたものでした。
そうすると、助走なしで走り幅跳びをしたり、ハンマーを振り上げなしで釘打ちをするようなものです。
ボールとのコンタクトまでしっかりと力を伝えるため、体幹や肩甲骨の可動域を使い、幅や距離を作る。
とても理にかなっています。
ボールの高低で変わる垂直回転と水平回転の比重
とここまで垂直回転と水平回転について述べてきましたが、それぞれの比重の理想はボールの高低で変わります。
垂直回転の割合を「スイングの前半1/4〜1/5」とアバウトに示したのもそのためです。
垂直回転と水平回転について振り返ると、「スイングの前半1/4〜1/5で垂直回転、残りの3/4〜4/5水平回転を行うことが理想」と述べられていました。
その「スイングの前半1/4〜1/5」などとアバウトな数字になっているのは、投球の高低によって垂直回転と水平回転の比率が変わるのが理由だそうです。
たとえば低めになるほどトップからバットを下方向に出さなければならず、重力や遠心力、サイクロイド曲線の理論なども踏まえると、しっかりと体幹を側屈させて垂直回転を大きめに使った方がいいでしょう。
逆に高めのボールを打つ場合は、バットを重力に逆らわせることになり、サイクロイド曲線などの重要性も減る。
したがって体幹の側屈を抑え気味にし、骨盤の回転に合わせた両肩の回転を強く意識し、早めに水平回転へ切り替えた方が対応しやすくなります。
低めは垂直回転が多め、一方高めは水平回転の割合が高くなるそうです。
高めのボールにバットをコンタクトさせるためには、肩甲骨の下方回旋と体幹の側屈から、肩甲骨の外転と骨盤の回転に切り替え、ヘッドの軌道を合わせていく必要があるようです。
相当なスキルが求められるため、練習が必要ですね。
バレルスイングのための体づくり

次に、バレルスイングのための体づくりについてです。
前述されているように、バレルスイングに求められる打球速度は158キロ以上で、スイングスピードは128キロ以上です。
そのスイングを生み出すためには、一定の体重が必要のようです。
128キロ以上のスイングスピードには除脂肪体重65キロ以上が必要
128キロ以上のスイングスピードを生み出すためには、除脂肪体重が65キロ以上あればよいということが、研究によって分かっています。
体重といっても除脂肪体重という指数になります。
除脂肪体重とは、脂肪を取り除いた体重のこと。
骨や内蔵などの重量も含まれますが、基本的にはその人の筋肉量を示すものだと考えられているようです。
平均的に体脂肪率が13%程度だと考えると、除脂肪体重が65キロ以上ということは、通常の体重で74.8キロ以上あれば良いということになります。
体脂肪率が13%であれば除脂肪体重は65キロ以上というのは、体重が74.8キロ以上ということになるようです。
あくまで引き締まった体格の男性の平均の体脂肪率から導き出した体重ですので、自身の体脂肪率から適正な体重を導き出してみて下さい。
ウェイトトレーニングで筋肉量を増やし、除脂肪体重とスイングスピードを上げよう
この除脂肪体重はウェイトトレーニングを行えば誰もが増やせるものです。
つまりホームランを打てる体を作ろうと考えた場合、ポイントとなるのは体格の大きさでなく筋肉量。
筋肉量が1キロ増えると、スイングスピードは1.3%速くなると言われています。
またスイングスピードが速くなれば打球速度が上がり、打球速度が5%上がれば飛距離は10%伸びるとも言われています。
さらに打球速度が上がればバレルゾーンの角度も広がり、安打率や長打率が上がることも分かっています。
だからこそウェイトトレーニングは非常に重要なのです。
除脂肪体重は筋肉量を示す指数です。
その筋肉量を増やす主な手段はウェイトトレーニングということになります。
筋肉量が増えるとスイングスピードが上がり、スイングスピードが上がれば打球速度が上がる。
打球速度が上がれば、飛距離が伸び、バレルゾーンの角度が広がり、安打率・長打率が上がる。
そういう正の相関関係があるようです。
ウェイトトレーニングで筋肉量を増やしつつ、求めたいスピードとコントロール
一方、スポーツの世界には「スピードとコントロールのトレードオフ」という言葉があります。
これは、スピードを重視するとコントロールの精度が下がり、コントロールを重視するとスピードが下がるという関係性のことです。
ウェイトトレーニングで筋肉量を増やしてスイングスピードが上がると、逆にミートする確率が下がる可能性があるということです。
しかし、トップアスリートになるためにはスピードとコントロール、2つの要素を同時に追求しなければなりません。
一般的にスピードを重視すると、コントロールが難しくなる。
逆にコントロールを重視すると、スピードが落ちる。
これを「スピードとコントロールのトレードオフ」というそうです。
トップアスリートになるためには、そこを同時に追求していく必要があります。
そこには「調整力」のトレーニングが重要になるのではないかと思われます。
調整力は、筋トレなどのトレーニングを実践の動きにまとめていく神経系のトレーニングと言われています。

この項をまとめると、トレーニングで「体重」と「スイングスピード」を上げ、身につけた「アッパースイング」をボールの軌道に入れちゃえば、強打者に!
もっと詳細を知りたい人は、トレーニング方法などもイラスト付きで分かりやすく説明してある本書をチェックしてみて下さい。
おわりに
いかがでしたか?
筆者はバッティングを我流で色々と試行錯誤をしながらも、低打率・低長打率は10代から変わりませんでした。
結果、まわりからスイングについてアレコレ言われ、心身ともにブレていました。
今回、自らバッティングを勉強しなおすことで、
・運動力学の視点からのバッティングの基本原則
・フライボールスイングが良い結果をもたらす科学的根拠
・フライボールスイングのメカニズム
が理解でき、明らかにスイング軌道が変化しているのを実感。
あとは、計画的にトレーニングをして、体作りと実践を積み重ねるのみです。
バッティングには正解はないとは言われています。
その中で、見た目ばかりにとらわれず、ぜひ本質的な部分を押さえながらトレーニングに取り組みましょう。
では。






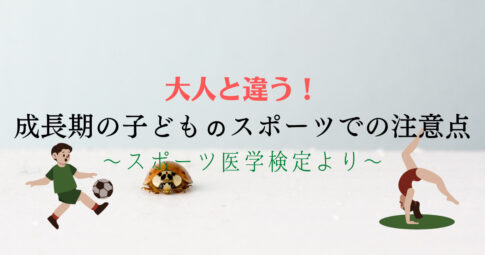
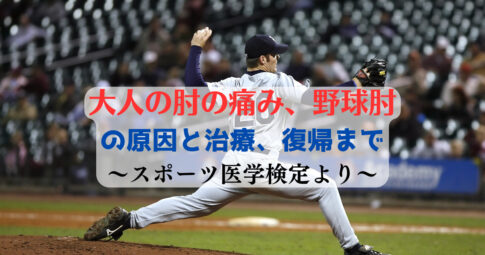
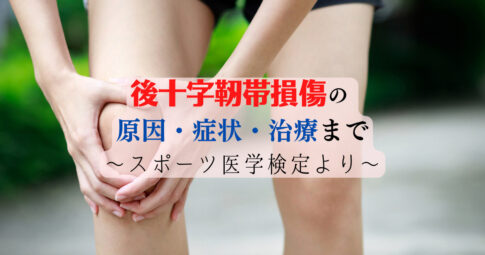
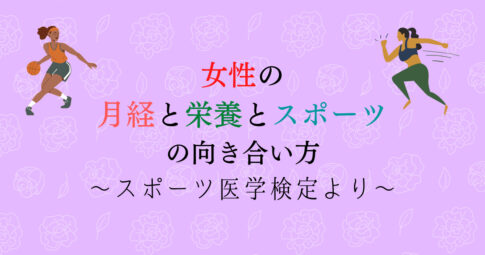
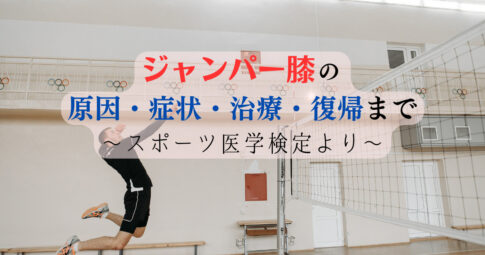

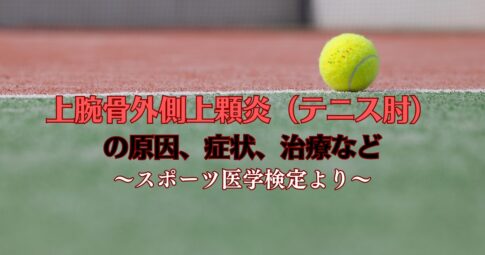
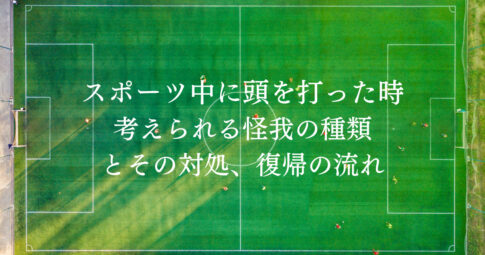

・中垣征一郎氏
・立花龍司