「成績が上がったら子どもが喜ぶ報酬を与える」vs「成績が下がったら子どもが嫌な報酬を与える」
どちらがパフォーマンス向上につながるのか?の答えは、前回の脳科学でひも解く自己効力感~子どものやる気スイッチが入る「報酬」とは~で、出ました。
今回は、そんな疑問にお答えする「自己効力感を脳科学的にひも解くシリーズ」最終話です。
「親がして欲しいこと」をお子さんが自分のものにして、ひとり立ちするために重要なお話しになります。

ポイントは「内発的動機づけ」という言葉です。
子育てに自己効力感を使うのは、ここに到達するためといっても過言ではありません。
今回も実験の内容と子育てに応用できるよう、分かりやすくご説明しています。
3分ほど読めば、親子で喜び合える豊かな子育ての一助になりますので、ぜひご一読下さい!
結局、報酬としては、お金やおもちゃといったモノしかダメなのか?
ヒトのモチベーション(やる気・動機づけ)には、
お金やおもちゃといったモノによるモチベーション(外発的動機づけ)
自分自身の中で「楽しい・したい」といった心の中のモチベーション(内発的動機づけ)
があります。
以下は、その2つのモチベーションのどちらが良いのかを明かそうとした実験です。
Murayamaのヒトへの実験
【課題:非常に楽しめて、没頭できるもの】
A.報酬群:成績が良いとお金を与える
B.対照群:学習が終わると定額の参加費を与える
↓(1回目が終了)
【結果】A群、B群ともにドーパミンや学習に関与する脳の場所が活性化
↓(休憩後、2回目は成績に関わらず報酬はなしと告げる)
【結果】Aの報酬群はドーパミンの関する脳活動が低下
一方、Bの対照群は1回目と同様、ドーパミンや学習に関与する脳の場所が活性化
休憩中の行動も、B群方が主体的に課題に取り組む回数が多かった。
まとめ
実験では、自分自身が「楽しい、したい」と思える「内発的な」モチベーションがあることは、お金といった外発的なモノがあるなし関係なく、ドーパミンに関する脳の活動が継続して働いています。
そして、自発的に課題自体に興味をもち、休憩中も課題に取り組むといった行動がみられています。
一方、お金という「外発的な」モチベーションに依存する形になると、お金という報酬がないと、ドーパミンに関わる脳活動が低下し、課題に取り組まなくなっています。
子育てへの応用
この実験で重要なことが2点あります。
課題が「非常に楽しめて没頭できるもの」であった点と、
その課題の「成績の結果によって金銭を与えたかどうか」という点です。
これまでの自己効力感シリーズで、「親のして欲しいこと」を子どもにしてもらうためには、
- 「子どもの好きなこと」「親のして欲しいこと」の深掘り
- 子どもにとっての「親のして欲しいこと」に対する「自己効力感」と「報酬期待感」を分析
- 「親のして欲しいこと」を段階づけて、難しさを調整
- 子どもの「出来た!」「楽しい!」を引き出す
という流れがありました。
その延長として、例えばお子さんが野球に関する「投げること」や「打つこと」が楽しくなっていたとします。
子どもの内発的動機になっているものにお金を与えるは逆効果

お子さんがすでに「投げること」「打つこと」を楽しんでいるとしたら、練習で投げた/打ったとか、試合で投げて/打って活躍したとか、そうした結果に対して、親がご褒美として「外発的な動機づけ」であるお金やものは与えない方が良い可能性があるということです。
もう子どもにとっては、「投げる」「打つ」ということが「内発的な動機づけ」になっているのです。
「投げる」「打つ」というだけで、脳内ではドーパミンや学習に必要な場所が活動しているということです。
親の余計な報酬がなくても「子どもの好きなこと」に関しては「ひとり立ち」しているのです。
これは勉強にしても同じと思われます。
子どもが文字に関心を持って、色々とテレビや本に載っている文字を読み出したとします。
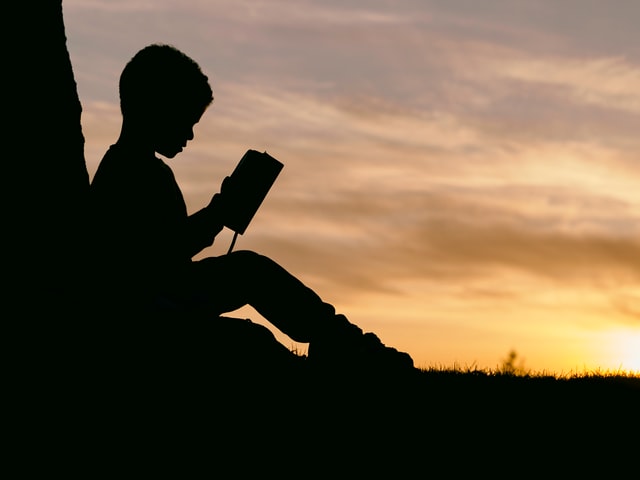
それは、そのこと自体を楽しんでおり、すでに「文字を読むこと」が内発的な動機づけになっているということです。
下手にモノやお金といった外発的な動機づけとなるような報酬を与えると、逆効果になる可能性があるということです。
ここまで来ると親にできることは、子どもの夢を聞いて、そこまでの道のりの整備をしてあげることくらいになるのでしょうか。
子どもの夢をかなえるために必要なことを一緒に考える。
大きな目標を叶えるための小さな目標をたてる。
目標のための手段や環境を整える。
子どもの成長に合わせて段階的に付き添いから見守りへ。
おわりに
いかがでしたか?
結局、「親の好きなこと」が「子どもの好きなこと」になってしまえば、あとは余計な報酬は必要ないということになります。
あとは環境を整えてあげることですね。
私はなんだかこの記事を書きながら感情が高ぶってしまいました。
エア子育てで泣けますね。
この記事を胸にとめて、愛する我が子の子育てをしていこうと思います。
読者にとっても、お子さんの「出来た!」がたくさんある豊かな子育ての一助になれば幸いです。
では。
今回の実験の内容は
行動変容を導く!上肢機能回復アプローチ 脳卒中上肢麻痺に対する基本戦略 道免和久(監修)竹林崇(編集)
を参考元にさせて頂いています。
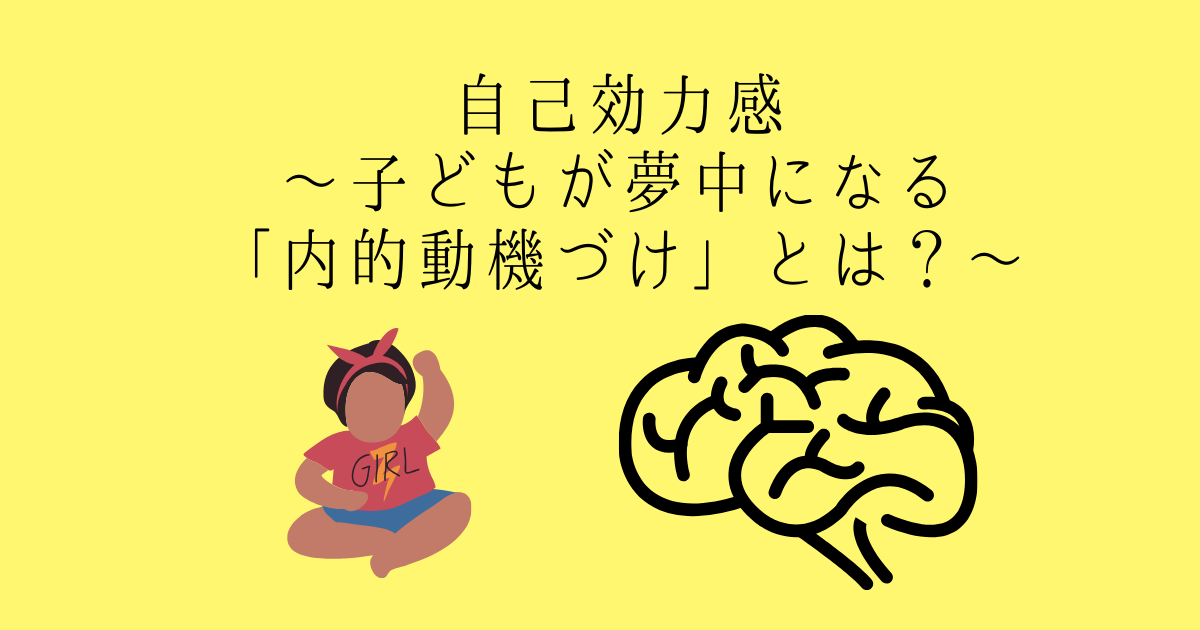
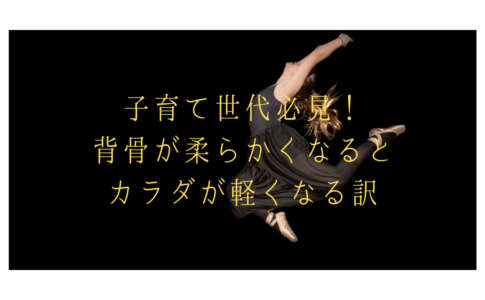
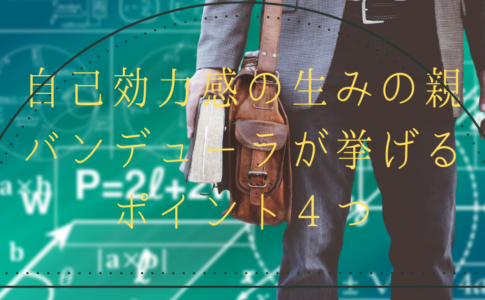
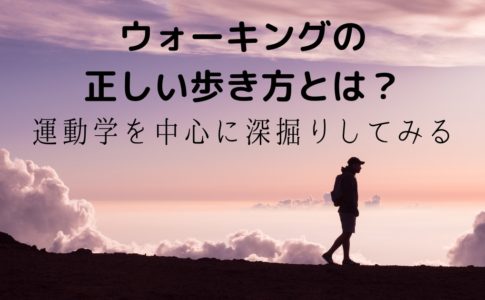
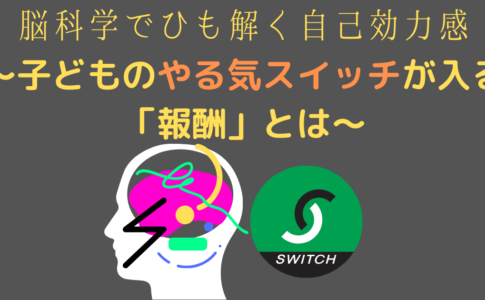



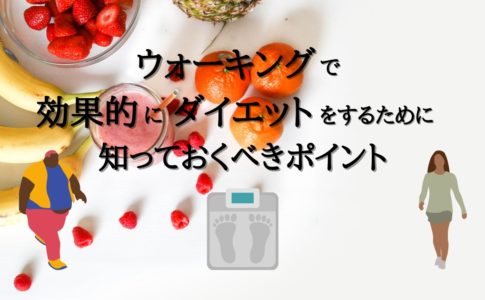

では、子どもにお金といった報酬を与え続けないといけないの?